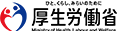有識者インタビュー

ジェンダー問題と日本企業の「男女の賃金の差異」
東洋大学 社会学部 社会学科 村尾 祐美子准教授
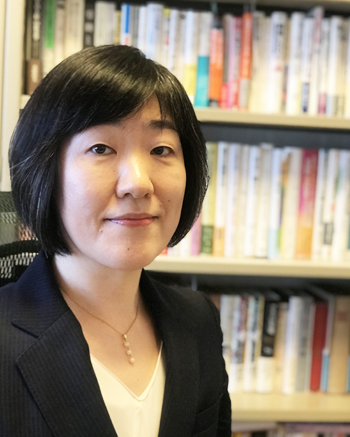
ジェンダー問題と日本企業における「男女の賃金の差異」について、労働社会学、ジェンダー論を専門とされていらっしゃる東洋大学の村尾祐美子准教授にうかがいました。
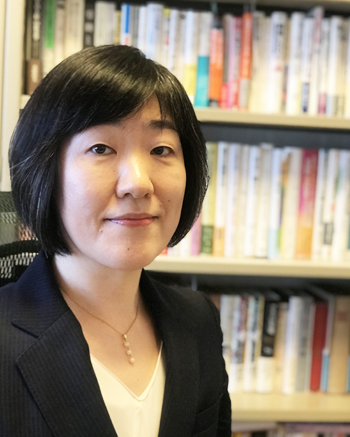
ジェンダー問題と日本企業における「男女の賃金の差異」について、労働社会学、ジェンダー論を専門とされていらっしゃる東洋大学の村尾祐美子准教授にうかがいました。
村尾 祐美子
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。博士(社会科学)。専門は労働社会学、ジェンダー論。第23回労働関係図書賞(共同受賞)、第6回女性学研究国際奨励賞、第1回日本労働社会学会奨励賞を受賞。第26期日本学術会議連携会員。第11期川崎市男女平等推進審議会会長。著書『労働市場とジェンダー』(東洋館出版社)。その他近著として「ジェンダー統計と性別欄削除 ―採用選考に関する事例を中心に―」(『国際ジェンダー学会誌』vol.22)、「性別分業における権力関係」(『岩波講座社会学 ジェンダー・セクシュアリティ』所収)、「公務員の採用選考と性別情報――差別と闘うツールとしてのジェンダー統計」(『大原社会問題研究雑誌』763号)など。
-なぜ、企業では女性活躍が進められているのでしょうか。企業が女性活躍を推進することのメリットを教えてください。
村尾氏:
村尾氏:
少子高齢化にともなう労働力不足を背景に、労働力確保や労働力の質の維持向上の実現のためには、女性も十分に能力発揮ができる企業であることが今後ますます重要になると企業が認識したことに加え、2016年に女性活躍推進法が施行されて、当初は従業員301人以上の大企業や国や自治体に、2022年4月以降は従業員101人以上の中小企業にも、女性の活躍のためのポジティブ・アクションが義務付けられたことが非常に大きいと思います。企業が自社の女性の能力発揮に取組む機運がここまで社会的に盛り上がり、さらには、持続・加速するという光景は、それ以前は見られなかったものです。
ポジティブ・アクションとは、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている人に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のことを言います。仕事の世界における女性活躍の文脈では、男女間に大きな格差があることを前提とした上で、それらの格差そのものや、格差の背景にある性別の役割分担意識や構造的要因を解消することを目的として行う暫定的な措置のことです。男女間の事実上の平等促進を目的とするポジティブ・アクションあるいは積極的改善措置は、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法に明記されており、差別ではありません。
女性活躍推進法以前は、女性の活躍のためのポジティブ・アクションに取り組むかどうか自体、個別企業の判断にゆだねられていました。
ところが、女性活躍推進法により状況は一変しました。国は、当初は従業員301人以上の大企業や国や自治体に、2022年4月以降は従業員101人以上の中小企業にも、女性の活躍という観点から自社の現状を把握し、課題を分析して数値目標を設定し、課題解決と目標達成のための事業主行動計画を策定して実行するというPDCAサイクルに取組むことと、また、女性活躍に関する情報を公表することを義務付けました。そのうえ、女性の活躍推進企業データベースという、企業が出している情報や事業主行動計画を検索・比較できる環境が導入され、各企業は、自社の女性活躍に関する取組状況に、求職者・投資家・消費者・同業者などの「社会の目」が向けられていることを意識するようになりました。こうして、女性活躍に関する課題に真摯に取り組む企業が多くなったのだと思います。
企業が女性活躍推進に取り組むメリットについては、先にも述べたように、少子高齢化社会の文脈のなかで、労働力の質や量の維持・向上がまず挙げられると思います。また、そうしたことを通じて、企業のサステナビリティや業績の向上も期待されているところです。さらに、女性がより能力発揮ができる職場は、経済面でもウェルビーイングの面でも女性にとってメリットがあるでしょう。加えて、そのような職場が実現することで、男性従業員にも恩恵が及ぶこともあるでしょう。もちろん、誰かにしわ寄せが行くようなやり方をすれば新たな問題が発生してしまうので、モニタリングしながら取組を進めることが重要だと思います。
さらに言えば、女性の活躍推進のメリットは、個別企業や個々の労働者にとどまるものではありません。国は女性活躍推進法で、一定以上の規模の企業に対しては、女性活躍推進の取組をしない選択を認めないという、踏み込んだことをしているわけですが、なぜそれが正当化されるかと言えば、男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる「男女共同参画社会」の実現を国が目指しているからです。企業におけるポジティブ・アクションの取組には、より良い社会の実現という、私たちが生きる社会にとってのメリットもあるのです。
-日本企業において「男女の賃金の差異」が生じる主な原因は何だとお考えでしょうか。
村尾氏:
村尾氏:
長い時間的拘束・転勤・勤務時間や仕事内容の変更に柔軟に応えるといった企業拘束度の高い働き方をする潜在能力が、昇進・昇格や賃金決定において必要以上に重視されているのではないかと考えています。
このような企業拘束度の高い働き方を、女性は男性よりも選びにくい。社会規範や慣行のもと、育児や介護などの無償労働の負担は女性に偏りがちです。そうした無償労働の重い負担をこなしつつ、無償労働の負担の少ない男性と同じくらい企業拘束度の高い働き方をすることは困難です。そのうえ、企業内の意識的あるいは無意識の偏見やそれを助長する社会制度という問題もあります。これらの複合的な結果として、男女の賃金の差異が大きなものになってしまうのです。
-企業選択における「女性の活躍推進企業データベース」の活用方法について、学生にアドバイスをお願いします。
村尾氏:
村尾氏:
同じ産業の2社以上の企業を比較してみるということです。私のゼミでは、毎年3年生が「女性の活躍推進企業データベース」を使い、それぞれ興味のある産業の複数企業を比較分析したプレゼンテーションをします。具体的には、データベース掲載の情報を、厚生労働省の女性活躍推進法特集ページにある「女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値」の資料に掲載されている「産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値」や、就業構造基本調査から算出した産業ごとの数値と組み合わせて、管理職女性比率と正規雇用女性比率を軸とするものと、雇用者女性比率と非正規雇用女性比率を軸とするものの2つの4象限マトリクスを作成し、分析対象の産業や企業が4象限に占める位置から特徴を把握します。
そのうえで、それぞれの特徴に基づいて、その企業の課題を考えます。次に事業主行動計画を見て、先に考えた課題に関する数値目標が入っているか、課題分析の適切さや課題に対する目標設定の適切さ、取組はゴール・アンド・タイムテーブル方式1になっているか、取組の働きかけの対象は女性限定か、それとも上司・男性労働者・企業内の仕組みも対象となっているか、働き方や組織風土の改善に関わる取組があるかなどをチェックしてゆきます。このような分析を行うことで、その企業が将来どのような方向に進んでいこうとしているのかがわかってきます。
学生たちは、就職活動の企業研究も兼ねて、実際に自分が受けるかもしれない企業を調べるので真剣に取り組んでいます。「女性の活躍推進企業データベース」では、他の媒体ではあまり見られない「有給休暇取得率」や「平均残業時間」などを見ることができるため、働き方を調べる上では良いツールだと思います。男子学生の間でも、女性が働きやすい企業は男性も働きやすいだろうという認識が広まってきており、自分のライフキャリアを考えた時にどのような働き方が望ましいかを真剣に考える姿が見られます。
もう1点、学生の皆さんに伝えたいのは「男女の賃金の差異」のデータの見方に関する注意です。算出方法が異なるデータが同じ欄に混在していることを知っておく必要があります。例えば、規定上、非正規労働者の賃金差異の算出に当たっては、パート労働者の人数をそのまま用いて算出する方法と、正規労働者の所定労働時間を参考に人員換算して算出する方法の2通りが認められています。人員換算した場合には、注釈・説明欄にその旨を記載することになっていますので、必ず注釈・説明欄も確認してください。算出方法により数値の意味が異なるので、男女の賃金の差異の比較は同じ算出方法のもの同士で行ってください。
1 達成すべき数値目標と達成までの期間の目安を示してその実現に努力する方法。