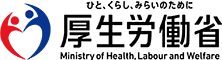女性の活躍推進・両立支援総合サイトトップ > 女性活躍・両立支援事例集トップ(事例検索) > 企業事例
2024年度
ポケットカード株式会社 (金融業、保険業)
仕事と育児の両立支援制度を導入し従業員のキャリア形成を後押し

認定マーク
企業プロフィール
- 設立
- 1982年
- 本社所在地
- 東京都港区
- 事業内容
- 金融業(クレジット事業、融資事業 等)
- 従業員数
- 404人 (うち女性 190人)
- 企業認定・表彰等
- くるみん認定、プラチナくるみん認定、えるぼし(認定段階3)、均等・両立推進企業表彰
取組内容
仕事と育児の両立支援
特徴的な制度・取組など
- 育児休業取得に関する情報を盛り込んだパンフレットを作成し、男性従業員やその上司にも配布
- 法を上回る、仕事と育児の両立に寄与する制度の導入