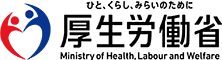具体的な取組の内容
「女性活躍推進プログラム」を通じ、管理職層への登用に向けて女性を育成
当行では2021年から、リーダーに求められる意識やスキルを身に着けることを目的として「女性活躍推進プログラム」を実施しています。本プログラムは募集型であり、参加対象者は年齢を問わず主任以上の女性です。期間は1年3か月で、主な内容として「キャリア研修」「外部研修」「オンライン学習ツールによる自己学習」「個別キャリア面談」があります。
「キャリア研修」は、外部専門家を招き、参加者各人のこれまでの仕事経験からキャリアビジョンや強み・弱みを明確にして、具体的なキャリア目標の設定やリーダーシップ力・思考力・企画力などの能力開発に取り組んでいます。
「外部研修」では、新潟県内外の企業との合同研修を通じて異業種交流を行い、新しい価値観に触れる機会を提供するとともに、創造性の発揚や人的交流を促しています。
「オンライン学習ツールによる自己学習」は、ビジネススクールが提供する経営に必要な知識やロジカルシンキング・デザイン思考などをいつでも動画で学ぶことができる自己研鑽メニューであり、育児や家事、趣味などと両立しながら自分のペースで学習できる環境を整えています。
「個別キャリア面談」は、外部キャリアコンサルタントによる面談と人事部による面談の2種類があり、各参加者の今後のキャリアを一緒に考える機会を設け、希望するキャリアの実現に向けて後押しをしています。
「女性活躍推進プログラム」を開始した2021年の参加者は15人でしたが、その後は参加希望者が増え、今年度は3期生として幅広い年齢・職位の25人が参加しています。主体性を重視したプログラムということもあり、研修では参加者が活発に発言するなど能動的な研修参加を通じた高い研修効果が得られているほか、プログラムへの参加をきっかけに支店長を目指すようになるなど意欲向上にもつながっています。
「女性取締役育成プログラム」を開始し、経営層への女性登用を促進
2023年12月から、女性経営人財の育成の強化を目的として、「女性取締役育成プログラム」を開始しました。本プログラムは選抜型で、これまでのキャリア、マネジメント経験、保有スキルなどを踏まえて選抜し、経営人財に求められる知識・スキル・経験を身に付けるためのさまざまな機会を提供しています。現在、管理職を中心に約40名が参加していますが、随時選抜者の拡充を図りながら、経営人財としての意識改革など一歩踏み込んだ育成・支援を目指しています。
「女性取締役育成プログラム」のカリキュラムは、実践を主体とするカリキュラムであることが特徴であり、「重要ポストへの戦略的配置」や「当社グループの会長・社長による講話とディスカッション」、「社外の女性経営者等による講話とディスカッション」、「未経験者が多い法人分野の研修」などの構成としています。
「当社グループの会長・社長による講話とディスカッション」では、第四北越フィナンシャルグループの会長、社長からの講話のほか、当行グループの経営環境や経営戦略を踏まえたディスカッションを通して、経営人財としての資質の向上を図っています。
「社外の女性経営者等による講話とディスカッション」は、業界を超えた知見を吸収して参加者の意識向上を図ることを目的としています。講師は県内外から招くとともに、民間企業の女性経営層に限定せず、これまでには新潟市の女性副市長による講演会も開催しました。
「未経験者が多い法人分野の研修」では、コンサルティング事業部や審査部など本部専門部署へ一定期間トレーニー派遣することにより、ファイナンス案件の組成や企業審査業務などを実践的に経験する機会を提供しています。
これらの課程を通じ、経営層に必要なスキルを習得するとともに、上位職への登用に向けた自信や意欲を高めることを目的としています。
「女性取締役育成プログラム」はグループとしての新たな取組ですが、女性活躍推進プログラム修了者が女性取締役育成プログラムに選抜されるような好循環を生み出すなど、女性経営人財の育成と組織風土作りを加速させたいと考えています。
地方銀行の広域連携により新しい価値観や創造性を育む
TSUBASAアライアンスは、千葉銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行、当行の10行が参加する地方銀行の広域連携の枠組みです。
2022年より、TSUBASAアライアンス全行が参加し、「TSUBASAクロスメンター制度」の運用を開始しました。同制度は、将来の女性幹部候補のキャリア形成やリーダーシップ向上を目指す10行横断型のメンタリング制度であり、メンターは各行の役員、メンティは女性幹部候補で、必ず他行同士でマッチングします。
オンラインによる面談を基本的に1年に5回以上実施しています。メンターが持つ知見をメンティが吸収したり、リーダーとしての視座向上を図るだけでなく、メンターにとっても、異なる価値観に触れる機会が新しい創造性の向上につながるなど、本制度はメンターとメンティ双方にとって非常に良い影響があると考えています。