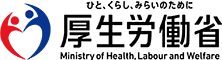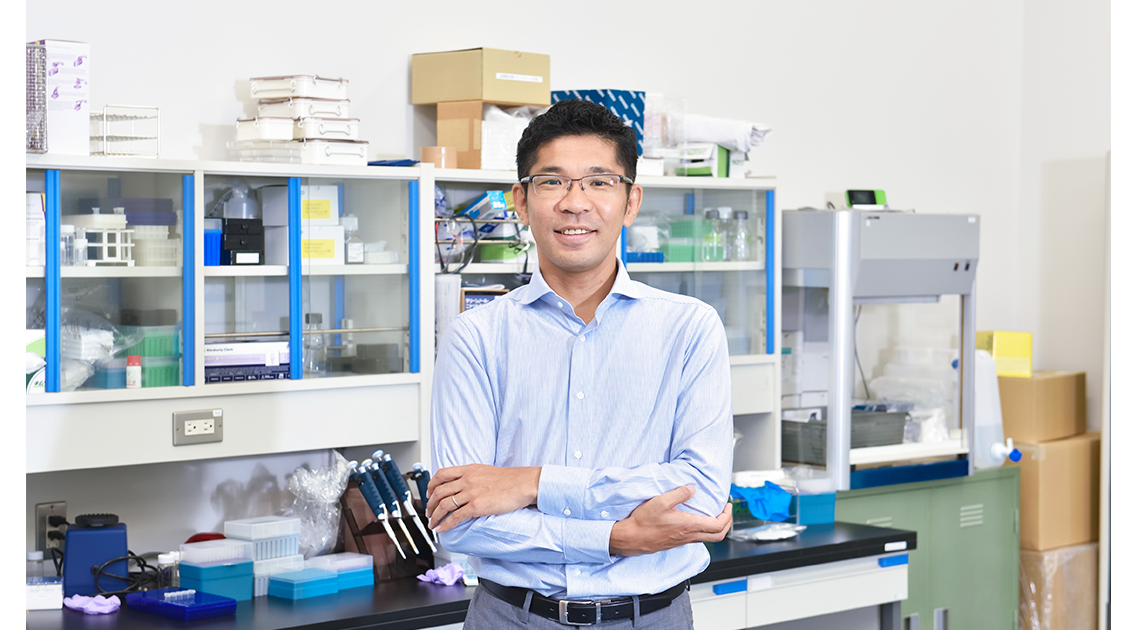女性の活躍推進・両立支援総合サイトトップ > 女性活躍・両立支援事例集トップ(事例検索) > 企業事例
2024年度
株式会社ヘルスケアシステムズ (サービス業(他に分類されないもの))
全ての従業員にとって「本当に働きやすい会社」を目指す
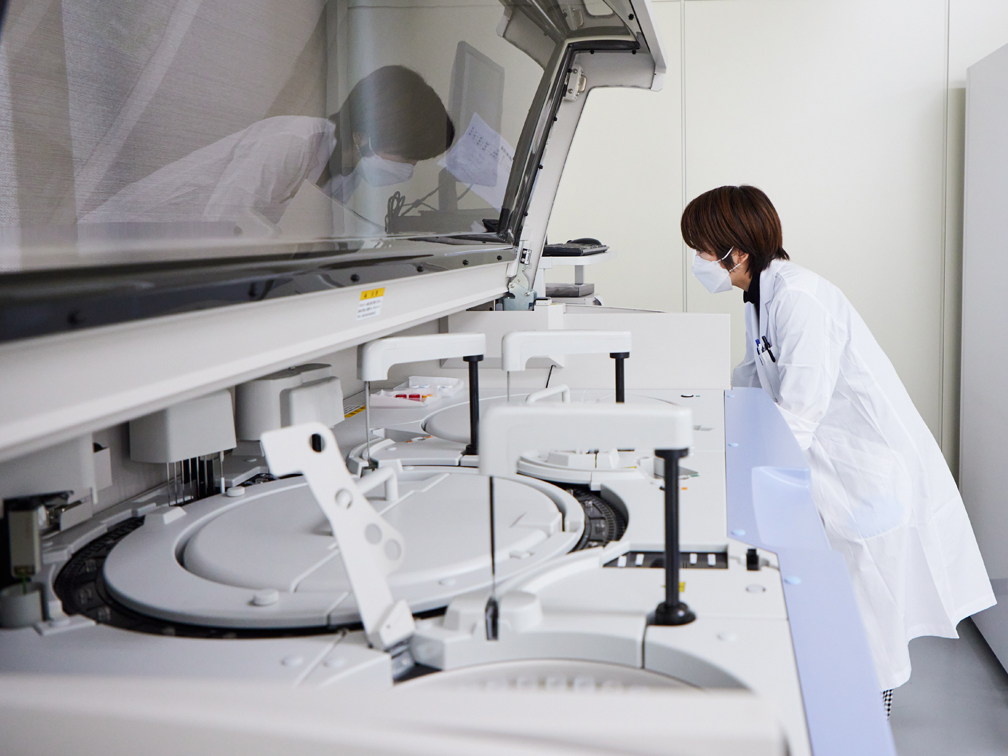
認定マーク
企業プロフィール
- 設立
- 2009年
- 本社所在地
- 愛知県名古屋市
- 事業内容
- 医療法人/サービス業
- 従業員数
- 70人 (うち女性 47人)
- 企業認定・表彰等
- くるみん認定、えるぼし(認定段階3)、プラチナえるぼし
取組内容
女性活躍推進 テレワーク フレックスタイム制 短時間正社員制度
特徴的な制度・取組など
- 在宅勤務、フレックス勤務、短時間勤務を活用し、柔軟な働き方を実現
- 男女公正な昇進基準のもとで管理職に占める女性比率が37.5%に
- 長時間労働を生み出さない仕組みづくりで女性の活躍を後押し