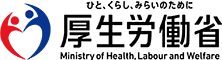女性の活躍推進・両立支援総合サイトトップ > 女性活躍・両立支援事例集トップ(事例検索) > 企業事例
2024年度
EY Japan株式会社 (サービス業(他に分類されないもの))
介護に関する従業員の不安を軽減し、将来の介護離職を防ぐ

認定マーク
企業プロフィール
- 設立
- 2010年
- 本社所在地
- 東京都千代田区
- 事業内容
- サービス業(日本国内のEYメンバーファームに向け、総務、経理、調達、IT、広報・ブランディング、マーケティング、人事、不動産業務、リスク管理等の業務を提供)
- 従業員数
- 非公開 (うち女性 非公開)
- 企業認定・表彰等
- えるぼし(認定段階3)
取組内容
仕事と介護の両立支援 テレワーク フレックスタイム制 短時間正社員制度
特徴的な制度・取組など
- 介護セミナーで幅広い年代の従業員に情報を提供
- 仕事と介護の両立に関する情報を集約したパンフレットを作成
- 柔軟な働き方の実現により介護離職を防ぐ