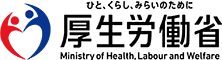女性の活躍推進・両立支援総合サイトトップ > 女性活躍・両立支援事例集トップ(事例検索) > 企業事例
2024年度
社会福祉法人 青谷学園 (医療、福祉)
週休3日制の導入と所定外労働の削減や、管理職育成のキャリア研修により女性職員のキャリアアップを支援

認定マーク
企業プロフィール
- 設立
- 1982年
- 本社所在地
- 京都府城陽市
- 事業内容
- 障害者支援、障害福祉サービス事業
- 従業員数
- 101人 (うち女性 57人)
- 企業認定・表彰等
- くるみん認定、プラチナくるみん認定、えるぼし(認定段階3)、プラチナえるぼし
取組内容
女性活躍推進 女性管理職登用 短時間正社員制度
特徴的な制度・取組など
- 管理職候補の女性職員がキャリア目標を立てて外部のキャリアアップ研修に参加するなど、自身のキャリアについて考える機会を提供し、上司とのキャリア面談を継続実施
- 週休3日制の導入により、1日当たりの労働時間が延びたことで、定時退勤への意識が高まり、所定外労働時間が削減
- 50歳以上の職員の要望を受けて職場の安全管理を行うなど高齢化対策に着手