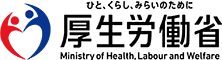障がいや難病のある子どもを育てる従業員の育児と仕事の両立支援として、次の制度を設けています。
※下記の勤務、休暇制度は取材当時(2024年9月)の情報です。2025年4月1日より、更なる両立支援に関する制度の改正を予定しています。
【参考】仕事と育児・介護の両立支援の拡充について
・短時間勤務制度
通常は1日あたり7時間30分等の所定労働時間(従事する業務によって異なります)を、6時間とする制度です。従業員が業務実態等に応じて始業・終業時刻を選択できるフレックスタイム制を導入していますが、乗務員など業務の特徴からフレックスタイム制が適用されない従業員についても、業務に支障がない範囲であれば、事由を問わずに時間単位の欠勤ができる、「フレキシブル時間」の制度を設けています。
・短日数勤務
育児・介護のため月4日間の休日を取得できる制度です。通常の休日と併せて週休3日とすることが可能です。基本的には会社が休日を指定します。短時間勤務制度との併用はできませんが、月単位で短時間勤務制度と短日数勤務制度のどちらを利用するか選択できます。
・養育休暇
月に5日まで、1日単位で取得可能できる無給の休暇です。短時間勤務制度または短日数勤務制度との併用ができます。
従来、短時間勤務制度は3歳まで、短日数勤務制度と月5日の養育休暇制度は小学校3年生まで、月3日の養育休暇制度は小学校6年生までと、子どもの年齢に応じて制度の利用期間に制約がありました。しかし、障がいや難病のある子どもを育てる従業員が働き続けるためには、当時の制度では不十分であると考え、まず、2023年10月に、障がいや難病のある子どもを育てる社員は、これらの制度を利用できる期間を子どもが中学校3年生までに拡大しました。
しかし実際に、障がいや難病のある子どもを育てる従業員のための両立支援制度を利用した従業員の声を聞くと、義務教育の終了以降も継続的に支援が必要な場面が多くあることがわかりました。そのため、制度改定から半年後ではありますが、こうした従業員が働き続けられる環境を整えるために、2024年4月から、障がいや難病のある子どもを養育する場合は子どもの年齢に関わらず、これらの制度を利用できることとしました。
これらの制度の対象は、子どもを「養育している」従業員であり、子どもが扶養から外れれば、制度利用の対象外となります。また、子どもに「障がい」や「難病」があるかは所得税法の規定する「特別障害者」に該当するかで判断していますので、制度の利用を希望する場合は、証明書の提出が必要になります。
当社では、障がいや難病のある子どもを育てる従業員に限らず、さまざまな状況にある従業員が働きやすくなるよう、制度改革を進めてきました。例えば、全従業員に対してテレワークを導入したほか、フレックスタイム制の全ての職場への導入などに取り組んできました。
また、「ワーケーション」という、会社とは異なる場所で業務に従事でき、仕事の幅を広げることができる制度などもあります。例えば旅行の合間で仕事をするなど、いつもと違う場所で思考を巡らせることで、新たな発想・気づきが生まれることを期待しています。