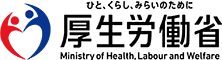女性の活躍推進・両立支援総合サイトトップ > 女性活躍・両立支援事例集トップ(事例検索) > 企業事例
2024年度
東ソー・エイアイエイ株式会社 (製造業)
男性従業員の育児休業取得促進により、男女の垣根を超えた育児と仕事の両立を目指す

認定マーク
企業プロフィール
- 設立
- 2001年
- 本社所在地
- 富山県富山市
- 事業内容
- 体外診断用医薬品(診断薬)の製造
- 従業員数
- 102人 (うち女性 23人)
- 企業認定・表彰等
- くるみん認定、ユースエール認定
取組内容
仕事と育児の両立支援 短時間正社員制度 男性の育児休業促進
特徴的な制度・取組など
- 育児休業の最初の5日間を有給化
- 育児休暇・介護休暇を1分単位で取得可能に
- 相談窓口と掲示板を設置し、仕事と家庭の両立支援の内容を周知